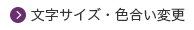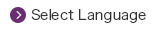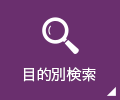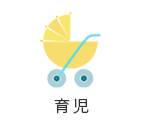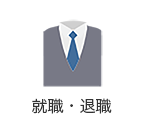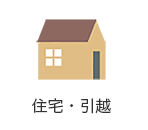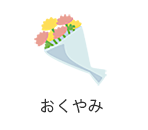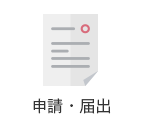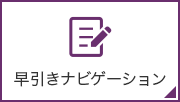定額減税補足給付金【令和7年度不足額給付】について
制度の概要
物価高への支援の一環として、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定していました。
本給付金は、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じている方に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付をするものです。
制度や事業の詳細については内閣官房および国税庁のホームページをご確認ください。
対象者
次の1または2の金額です。
- 「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額(1万円単位に切り上げた金額)
- 原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
給付額
次の(1)または(2)に該当する方です。
(1)当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で不足の差額が生じた方


※推計所得税額とは、令和5年分所得等をもとに計算(推計)された令和6年分所得税額で、当初調整給付の際に使用しています。
※所得税額(実績)とは、令和6年分の確定申告や年末調整等を実施したことで確定した令和6年分所得税額です。
※定額減税可能額(所得税分)=(本人+扶養親族)×3万円
※個人住民税の扶養親族数は、令和5年12月31日時点の状況で判定するため、令和6年中に扶養親族に変数があった場合でも、定額減税可能額(住民税所得割分)は変動しません。
(2)A~Cのすべてにあてはまる方
A令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である
B税制度上、「扶養親族」から外れており、扶養親族等として定額減税対象外である
C次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)



(3)その他
(1)、(2)のほか、低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しておらず、かつ以下のいずれかの要件に該当する方は「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当し、支給対象となる可能性があります。対象となると思われる場合は、担当課にお問い合わせください。
- 令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
- 令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象になった方
- 令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう者)で、本人として当初調整給付の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった方
※低所得世帯向け給付とは次のことを指します。
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
給付の手続き
令和7年7月以降に、給付対象者宛に支給決定通知(ハガキ)または確認書を送付する予定です。
通知ハガキが送られてきた方【7月下旬の予定】→原則、手続きは不要です
公金受取口座の登録をされている方、または、過去の給付金事業等から村が保有する口座情報に該当がある方については、支給決定の通知ハガキを送付します。
- ハガキの圧着面に記載の口座への振込を了承する場合は、特に手続きは不要です。
- 上記記載の口座以外の口座に振込を希望する場合、または給付金の受給を辞退する場合は、次のとおり手続きが必要です。
- ハガキに記載の二次元コードからオンライン申請
- 口座変更または給付金辞退申請書(書面で役場総務企画課へ提出)
確認書が送られてきた方【8月中旬の予定】→以下のいずれかの手続きが必要です
| 区分 | 手続期限 | 申請方法 |
| オンライン | 令和7年10月31日まで |
スマートフォンやパソコンから申請 (確認書に記載の二次元コードからオンライン申請のページにアクセスして申請を行っていただきます。) |
| 書面(確認書の郵送) | 令和7年10月31日まで(消印有効) |
村から発送予定の確認書に必要事項を記入のうえ返信 【口座の登録や変更が必要な場合、以下の書類を添付してください】 ・口座情報確認書類(通帳またはキャッシュカード)の写し ・本人確認書類(免許証、資格確認書、保険証、マイナンバーカード等)の写し |
給付の時期
- 通知ハガキが送られてきた方:口座の変更等がなければ、通知発送から3週間前後で振込予定です。
- オンラインまたは書面で手続きした方:受付後、不備等がなければ、順次給付(口座振込)します。
※オンライン手続きの場合、書面手続きよりも早く振り込まれる予定です。
提出または申請が行われなかった場合等の取扱い
- 令和7年10月31日(金曜日)までに確認書の提出または申請が行われなかった場合は、支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなします。
- 確認書または申請書の不備による振込不能等があり、村が確認等に努めたにも関わらず、確認書または申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなします。